2022年7月にDFreeを導入いただいた社会福祉法人南高愛隣会さま。
法人全体でDFree活用を推進いただいている生活介護事業所『TERRACEひだまり』管理者の吉田さまに、DFreeの取り組みについてお話を伺いました。
(インタビュー実施日:2024年8月22日)

排尿のタイミングが見える。それが支援の出発点に
社会福祉法人南高愛隣会が運営する「TERRACEひだまり」では、排尿に関する支援を必要とする利用者が多く、ケアの精度を高めることが現場の課題となっていました。
その中で、排泄予測デバイス「DFree」の導入に取り組み、支援の新しい形を模索してきました。
特に障害福祉の現場では、「行きたい」と言えない方や、感覚的に気づけない方が多くいます。DFreeを活用することで、排尿のタイミングを"見える化"し、支援者が適切な声かけを行えるようになりました。
活用方法:まずは短期間のアセスメントから
「TERRACEひだまり」では、DFreeをアセスメントツールとして活用しています。まず1週間程度装着して排尿の傾向を把握し、トイレ誘導のタイミングを調整するという流れを基本としています。
最初は1時間の装着から始め、徐々に慣れてもらうようにしています。装着の目的を理解できる方では、長期利用を行うケースもあります。
成功事例:失禁がなくなり、DFreeも卒業へ
法人内の就労支援事業所で従事されているご利用者の中には、作業に集中するとご自身の排尿の感覚に気づけず、失禁してしまう方もいらっしゃいます。
DFreeを活用し、通知をもとに支援者がトイレのお声かけをするようにしたところ、失禁がなくなり、最終的にはDFreeも不要となるまで改善が見られました。
ご本人の自信にもつながり、支援側も安心して業務に取り組めるようになりました。
法人内での活用についてはいかがでしょうか?
法人内の全体研修や役職者会議の場でこうした事例を紹介し、他事業所にもDFreeの活用を広げる活動をしています。
若手職員が中心となって使い方をレクチャーし、動画マニュアルなども活用しながら、無理なく現場に浸透する体制を整えました。
その結果、現在では法人内の4事業所でDFreeの導入が進み、活用が定着しつつあります。
さらに、25年7月からはより軽量・薄型化された「DFree Slim」への切り替えを行いました。これによりDFree使用のハードルが下がり、活用の幅がさらに広がっていくことを期待しています。
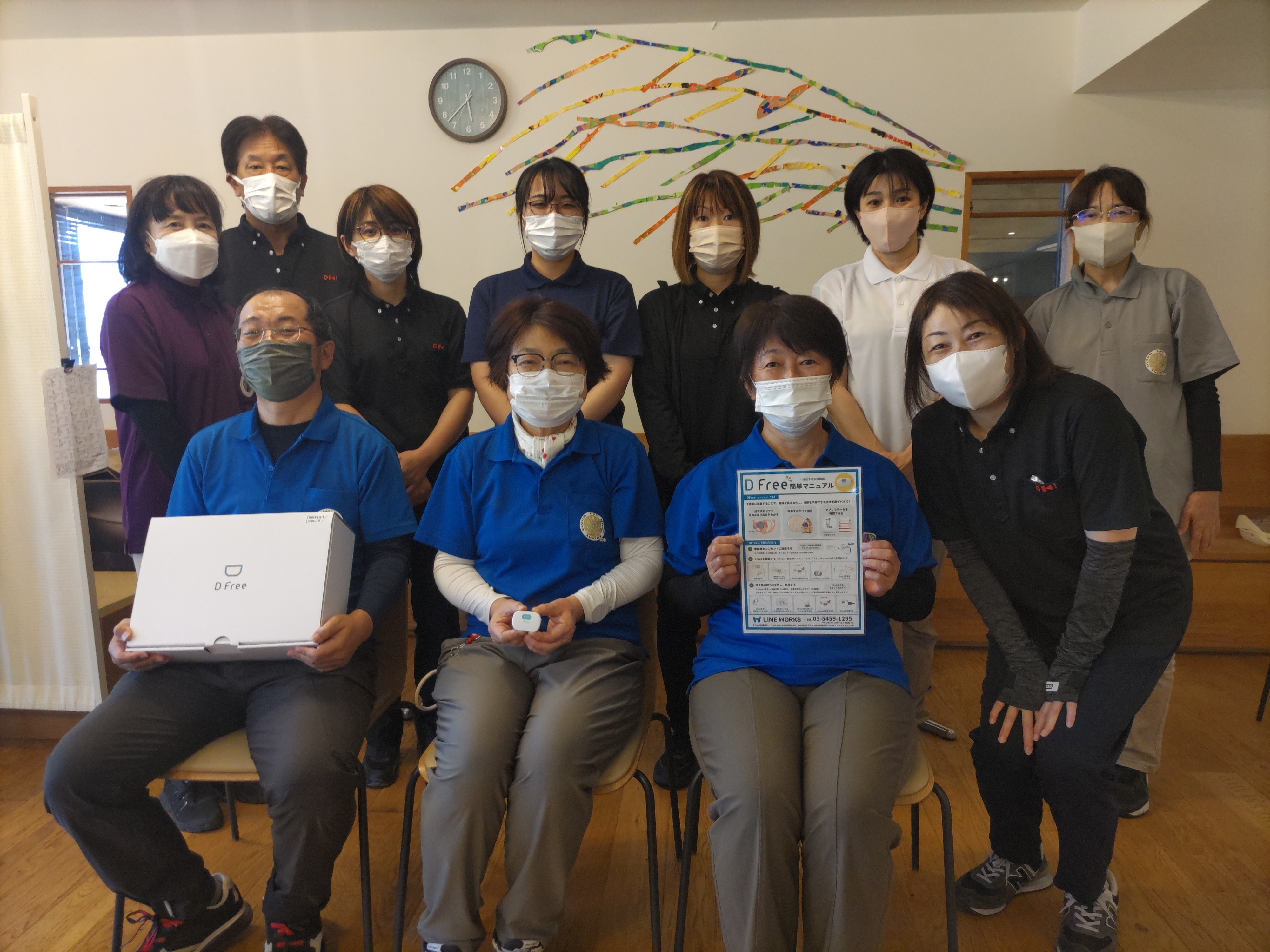
まとめ ~ DFreeカスタマーサクセスより ~
日頃から吉田さまを中心にDFreeをご活用いただき大変嬉しく思います。
DFreeを活用することで、「失敗しないトイレ誘導」や「本人の気づきを支える支援」が実現し、障害福祉の現場に新たな排泄ケアのあり方が生まれています。
短期アセスメントから日常的な支援、さらにはデータに基づいた分析まで、DFreeは支援の幅を広げるパートナーとしてこれからもお手伝いさせていただきます。
